|
Toyota Prius (2016/4) 前編 その1 |
|
|
|
|
|
今から18年程前の1997年12月に発売された初代プリウス (NHW10 写真1) の「21世紀に間に合いました。」というキャッチコピーは今でもハッキリと覚えている。なんたって初代プリウスは世界初の量産ハイブリッド専用車だから、それゃあインパクトは絶大だった。当時のベースグレード価格は215万円で、当時の噂では「21世紀へgo!」をモジッたということだった。まあ何れにしても200万円台では最初は大赤字だったに違いないから、価格だって原価計算とは無縁のモノだからインパクトのある価格にしておいた、ということだろうか。 この初代プリウスのアウターサイズを見ると、全幅1,695㎜ という5ナンバーサイズであり、当時のカローラの 全長4,315 x 全幅1,690㎜ x 全高1,385㎜、ホイールベース2,465㎜ と比べると初代プリウスは全長が40㎜ 短く、ホイールベースは95㎜ 長いがほほ同一サイズであり、クラスとしてはカローラと同じだった事になる。価格としては初代プリウスが発売された1997年モデルのカローラ1.5 LX (8代目 E110) が 121.2万円だったから、プリウスの 215万円は90万円以上高かった事になり、結局当時プリウスを買ったのは低公害をアピールしたい官公庁や大企業であり、個人で買うのは余程の新しいもの好きで余裕のあるユーザーだった。 2代目プリウスは初代から6年後の2003年9月に発売された。この2代目 (NHW20) は初代に比べて多少拡大されて、全幅は1,725㎜ の3ナンバーサイズとなったし、ホイールベースも150㎜ 延長されるなど一クラス上に迫るサイズとなった。この時代のカローラは9代目の E120 であり、サイズは5ナンバー枠を維持していたから、この時点でプリウスは「カローラにモーター載っけただけで百万円高い、なんてぇ事は言わせねぇぞ!」ということろか。それでもベースグレードは初代の215万円 を維持していた。 |
|
|
|
|
|
そして3代目のZVW30 が発売されたのは2代目からまたまた6年経った2009年5月であり、ここでベースグレードの価格は先代よりも10万円安い205万円となった。本当ならもう一息頑張って199万円なんて事にすれば良かったのに、何て安易に考えるがトヨタにしてみれば恐らく205万円がギリギリのところだったのだろう。ところが何と、この3代目にフルチェンジした後も2代目プリウスは単一グレードとしてビジネスユーザー向けに189万円で販売が続行され、その後2011年末迄販売されていた。 この3代目はモーターも一新されて 3JM となったが、それ以前の 1CM や2CM とは全く思想を変えて高出力、低トルクとなった。CM タイプのモーターは最大トルクが300~400 N-m と大きいのに対してJM は200 N-m と低く、しかし最大出力は上がっていることから高回転 (ガソリンに比べれば中回転) 域でのトルク自体はアップしているのだろう。 それで新型はといえば、またまたモーターは一新されて1NM となり、スペックを見るとトヨタには珍しく先代の 3JM に比べてパワーもトルクもダウンしてる。 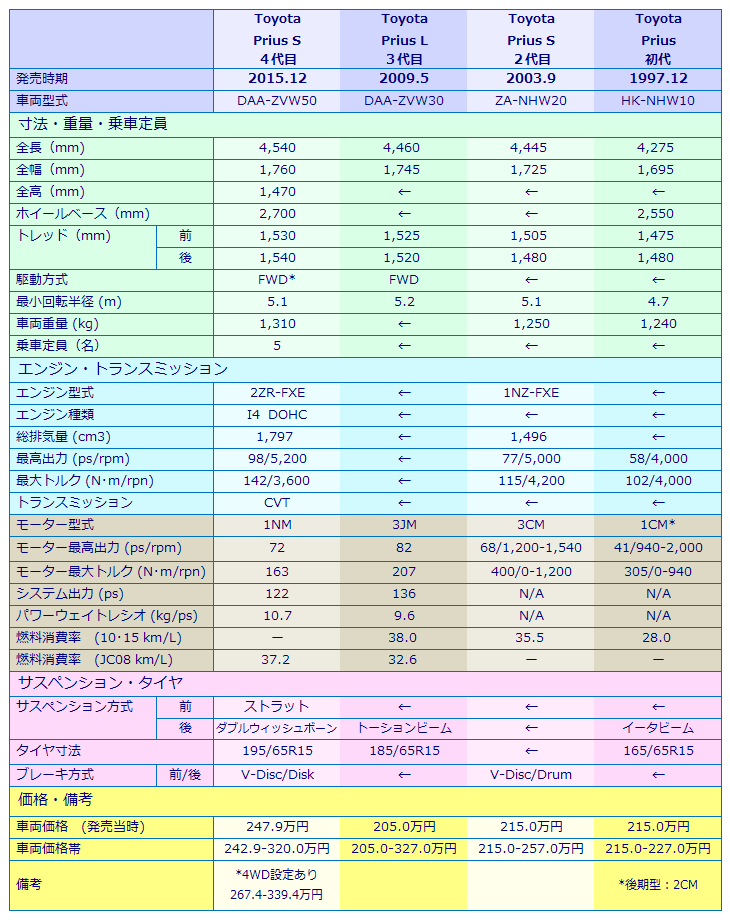
その新型の価格はといえば一番安い "E" でも240万円以上と先代に比べて40万円以上の値上がりだが、これはもうワンラン上に行ってまったようだ。その代わりに200万円前後のハイブリッド車としては 176万円よりのアクアがあり、そのアクアはといえば発売直後のモデルに試乗したら、アット驚く低剛性のヨレヨレで普通に走っていても不安が付きまとうような最悪の走りを見せてくれた。 それでもアクアの人気は絶大でこのところの登録台数ではプリウスを抑えて堂々の一位だ。それにしてもあの出来の悪いクルマが何でそんなに売れるのかと疑問に思い、お台場のメガウェーブで試乗してみたらば思いの外良かったが、後で気が付いてみたらば試乗車は足回りの部品を変えてボディーを補強したスペシャルモデルのG's というモデルだった。 そこでその後にディーラーで一般的なモデルにも試乗したが G’s 程ではないにせよ少なくとも初期型の不安定さは消えていた。ということは少なくとも2014年12月のマイナーチェンジ後、すなわち後期型からばコストパフォーマンスを考えれば買う価値はありそうだ。 ところでプリウスには派生車として大型のバッテリーに充電機能を持ったプラグインハイブリッド方式の PHV と7人乗りのプリウス α (アルファ) があり、PHV は外観上では殆ど標準のプリウスと変わらないが、α は外観上、特にボディ後半が異なっている (写真4) 。 |
|
|
|
|
|
それでは本題に入り、先ずは内外装についての紹介をするが、いつもの様に既に2月28日からの日記 早速、新型プリウスのエクステリアを見てみると、一見して従来の腰高な印象から低くスマートに変身しているのが判る。特にリアは写真で見るとキープコンセプトのようだが、実車を見ると随分雰囲気が変わっている。先代は腰高感がかなりあり、これではお世辞にもスタイリッシュとは言えなかった訳だが、逆にそれがプリウスの特徴だと思っていたくらいだ。 フロントでは高さ方向に狭い (細い) ラジエターグリルやバンパーには台形のエアインテイクなどのモチーフは変わらないが、勿論サイズや詳細な形状は違う。そして一番の相違点はヘッドライトで、新型は大きくつり上がった特徴的な形状をしている (写真9) 。 サイドビューを比較すると、今回の目玉である低重心化のためにルーフが低くなっているのが判る‥‥という程でも無かったが、確かにBピラー以降のラインは先代よりも低いのは判る。またBピラー以降はウエストラインも大きくキックアップしている。リアでは新型のテールランプの斬新なデザインが目を引く (写真9) 。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
サイズ的にはホイールベースは同一だが全長は新型が 80㎜ 長い。 |
|
|
|
|
|
ヘッドランプは当然ながら全グレードで LED タイプであり、クリアランスランプとフォグランプも LED 方式となっている。リアのコンビネーション (テール&ストップ) ランプも勿論 LED 方式だ (写真10~11) 。 リアのラゲージスペースは先代と比べると何となく幅が狭く感じるのはリアサスの張り出しが多いからであり今回からリアにダブルウィシュボーンを採用したデメリットでもある。これはプリウスに限らずしょぼいサスペンションを使用したほうがラゲージスペースが広くなるのは一般的な傾向だ (写真12) 。 今度は床板をチラッと捲ってみると中からはフリルの付いた‥‥ではなくて、ジャッキやレンチが入っていた (写真14) 。なお、バッテリーはリアシートの真下に搭載されているのでリアシートのバックレストを倒すことが可能だが、多少の段差があって床面とフラットにはならないが、長ものを積むことは出来る (写真15) 。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長くなってきたのでこの先は ”前編その2” に続く。 |
|








 写真8
写真8





