|
Subaru Forester 2.0 Hybrid (2018/9) 前編 その1 |
|
|
|
|
|
スバル フォレスターはプラットフォームをインプレッサと共有するクロスオーバーSUVとして 1997年に 発売された SF系 が初代となる (写真2) 。この初代インプレッサのルーツとなるのは1995年にインプレッサスポーツワゴン(GF型)をベースにクロスオーバースタイルとしたインプレッサグラベルEXで、しかしこれはリアにスペアタイヤを背負うなど妙に本格的で使い辛い事もあり成功には至らなかった (写真1) 。 初代フォレスター (SF) のエンジンは発売当初は何と 2.0Lターボ(250ps/31.2kgm)のみだった。その後自然吸気 (NA) エンジン車も追加されたが、この頃の感覚が今でも残っていてフォレスター=ハイパワーターボ車というイメージが今でも残っている。当初NAモデルは 2.0L (137ps) のみで 2.5L (167ps) が追加されたのは 2000年と発売から3年後だった。 2代目 (SG) は初代より5年後の 2002年に発売され、エクステリアはキープコンセプトでエンジンは2.0L のターボ (SFよりデチューンされて220ps) とNAで 2.5L NA は設定が無かったが、2005年に Sti バージョンとして 2.5L ターボ (265ps) モデルが発売された (写真3) 。 3代目 (SH 2007年) は従来までのステーションワゴン的なものからよりクロスカントリー的なものとなり、フロントグリルも全く違うデザインとなった (写真4) 。これは米国では好意的に迎えられたが国内のスバリストからは評判は良く無かったと言う。エンジンバリエーションはそれぞれ型式は同じながら 148ps と多少パワーアップした 2.0L NA および ターボ (230ps) で、後期型 (2010年) からは NA が新型エンジンとなり、また例によって 2.5L ターボモデルが追加された。前期型ターボには当時下記の簡易試乗記があるが、結果は非常に良かった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
そして 2012年には 4代目 SJ へと FMC された。このモデルでは後期型 XT 2.0L ターボ (280ps) モデルに試乗している。正直言って試乗記では無く簡易試乗記としたところが、個人的な思い入れの浅さを表していると思われそうだが、当時はこのクラスのクルマは全て簡易試乗記だったという経過がある。(お〜っ、上手く誤魔化した)。 そしてフォレスターは今回の FMC にて 5代目 SK へと FMC された。ここで先代 SJ と新型 SK の主要モデルのスペックを比較しておく。今回の目玉は新たにハイブリッドモデルが追加された事だが、ハイブリッドとはいえモーター出力は 13.6ps と小さく、言ってみればマイルドハイブリッドの部類で、しかもエンジンは NA モデル (2.5L) よりも非力な 2.0L (勿論NA) であり、これではモーターでパワーダウンした分を補う事が出来るかという懸念がある。そして先代には設定のあった 2.0L ターボモデル XTに相当するモデルが今のところは無い。しかも新型のハイブリッドは価格的には旧XT と等しく、それでパワーは圧倒的に劣るという現実を、果たしてスバルユーザーが納得するだろうか。
|
|
|
さてこの試乗記前編では内外装写真から始めるのは何時もの通りだが、これまた何時も通りで既に日記に於いて、よりサイズの大きい写真を掲載しているの。 と言う事で、こちらでは趣向を変えてみる事にして、ここでは試乗車と同じハイブリッドモデル Advance と先代のターボモデル XT を比較する事にした。実はハイブリッドの場合、グレードはこのアドバンスのみとなっている。ガソリン 2.5L NA ではツーリング、プレミアム、X-ブレイクと3グレードあるのだが、これじゃハイブリッドは売れない、と見ているのが見え見えだ。価格は前述のようにほぼ同じ (約310万円) で、両車共オーディオレスの為に実際には10万円以上が上乗せとなる。 それでは早速斜め前後から新旧を比べると、先代 SJ は更にその前の SH でフロントグリルを全く脈絡の無いデザインに変えた事を綺麗さっぱり忘れ去り、従来のフォレスターのイメージ戻しているが、今回の新型も一見したところは正にキープコンセプトで、やはり SH で痛い目にあった経験は生きているのだろう。それにしても SH のデザインを決定した責任者はいま如何なっているのか気にかかるところだ。なおリアビューはランプ類が違うので少しイメージが異なっている。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
今度はフロント同士を比較すると、新型は全幅が 1,815㎜ と先代の 1,795㎜ より20㎜ワイド化された。なーんだ 20㎜ か、何て言う無かれ。BMW3シリーズが日本向けにドアハンドルを別部品に変えてまで全幅1,800㎜ を死守している事でも判るように、日本のファミリーマンションに多い立体駐車場では全幅が1,800㎜ を超えると申込すら出来ないのが実情となっていて、この場合は地上の平面部分か外部の駐車場と契約する必要が出てきてしまうのだが、これに問題は無いのだろうか? 若しかしてスバルオーナーはマンションではなく一戸建てが常識なのか? まあここで「マンションが戸建てか」何ていう面倒な議論をする積りは無いが、一般的に言って高学歴者はマンションを、それ以外は戸建てを好む傾向があるが、では高学歴って何かというと、以前は大学 (学部) 卒でも高学歴だったが、最近の若い世代では高学歴=大学院修了、いわゆる院卒の事を言うのだそうだ。まあ分数や BE 動詞が判らない大学生を高学歴とは言えないよなぁ。 おっと、話が逸れてしまった。えーと何をやっていたかと言うと‥‥そうそう、フロントの比較だった。フロントフェイスは基本的に同じで、グリルの基本形状も同じだが高さが高く、しかもスバルマークから左右に広がるメッキモールも太くなり、一見して迫力が増している (写真8) 。 サイドビュー (写真9) では新型が全長 4,625㎜ x 全高 1,715㎜ ホイールベース 2,670㎜ 、先代は全長4 ,610㎜ x 全高 1,715㎜ ホイールベース 2,640㎜ だから、結局全長が15㎜ 長くホイールベースも 30㎜ 長くなったが、まあこの程度ではほぼ同一サイズと言っても良い程度だ。 それでは真後ろからの比較 (写真10) はと言うと、新型のリアコンビネーションランプ形状はリアゲードまで侵入していて、その形状は “コ” の字型となっている。要するに面積的にも大型化された事で、一見したイメージが随分と高級になったようにも思える。リアゲートを持つクルマの場合、ランプをピラーのみとすると妙に小さくなり、何と無く昔の ”ライトバン” を髣髴させて安っぽくなる傾向がある。 リアラゲージエリアについては新旧で大きな違いは見当たらないのはサイズ的に殆ど同じだからであろう (写真11) 。 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
続きはその2にて‥‥。 |
|





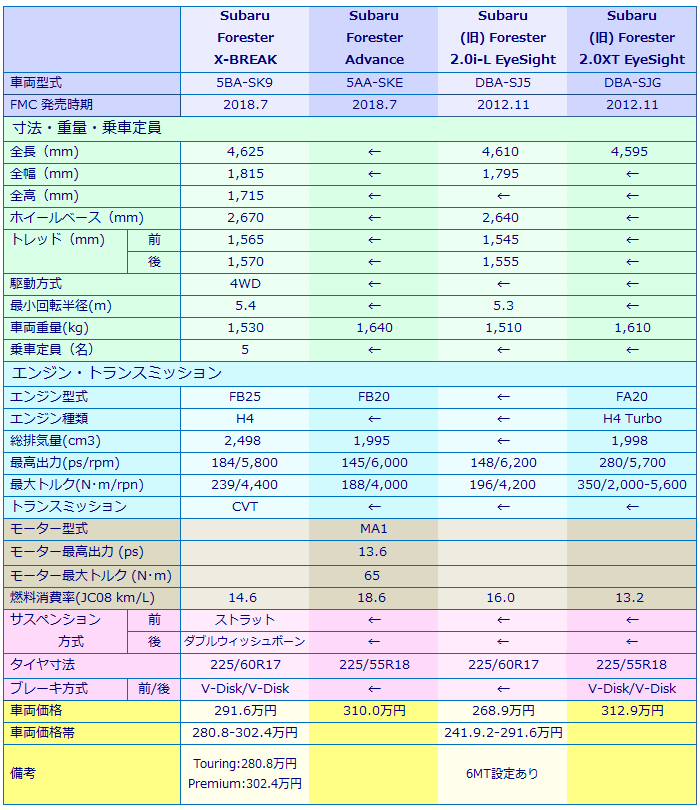


 写真9
写真9
